
「写真は言葉であり、言葉は音楽でなければならない」−成瀬功
初詩集をまとめていた頃、「なぜ詩を書くのか」とか、「詩を書くことに意味はあるのか」とか、色々言われました。実際、当時の私の写真の師匠からも、「詩と写真とどっちが大事だ」という、考えれば意味不明な質問をされ、「いまは詩です」と素直に答えた私はその場で会社をクビになりました。理不尽な話です。笑
私にとって詩を書くことは写真では表現できない部分を補うことであり、写真を撮ることは、詩の世界をビジュアル化することで非言語で直感的にする、という意味があり、すなわち写真と詩はお互いに補完関係にあり、根本では同義ですらあるのです。
この話は長くなりますので、何回かの記事に分割してお話ししましょう。
まず、詩についてですが、私が詩を書き始めたのは、中学時代に遡ります。まだ「詩を書く」という意識すらありませんでしたが、とにかく内側から溢れるものを吐き出したい、という欲動が言葉となり、自然と詩の形をとるようになったのです。
そして、中学を卒業するときに担任の先生がクラスに配布したのが、谷川俊太郎先生の名作、「生きる」でした。
写真も言葉も、根源的には音楽だ、と私の創作について書きましたが、谷川俊太郎先生の「生きる」は、その言葉の意味以上に、まさに音楽としての言葉の表現に卓越していると、読んだ瞬間に感じました。そして、「いつかこんな言葉を奏でたい」と強く思ったのをはっきりと覚えています。
言葉、詩と音楽は、切り離せない関係にあると感じています。言葉に音楽性がなければ、その言葉に命はなく、訴えかけるものがないとさえ思っています。そんな私が、処女作である「記憶の道端」を書いた時分、一番影響を受けたのは、サミュエル・ベケットの散文でした。
それは矛盾を感じさせるかもしれません。ベケットの散文には音楽性があるのか、という問いがあるでしょう。私は、その時もっとも必要としていた音楽が、ベケットの散文の中にあると感じたのです。文法を無視し、文章として意味すらないように思えるその散文は、日本語への翻訳にさぞ苦労されたと思います。
彼は原文を英語で書き自らフランス語に訳したり、その逆を行ったりして、色々と実験的な書き方をしました。そして、いずれの言語でも主語がなかったり文法的に文章になっていなかったり、と、破天荒な創作で一部賞賛されたり、一部では「作品ではない」と無視されたりしました。初めてそれを読んだ時の衝撃を、忘れることができません。こんな言葉が存在するんだ、と感動で泣きたくなるほどでした。翻訳が素晴らしかったことも、大きな一助になっていたでしょう。
私にとって、ベケットの散文は楽譜のようでした。それも、かつてのモーツアルトがそうであったように、それまでの常識を無視したまったく新しい音楽に感じました。Wikipediaを参照してみましょう。
「散文においては、特異な光景、切り詰めた語り、錯綜した描写、物語ることそのものを突き詰めたようなモノローグなどによって独自の世界を確立し、その傾向は三部作(とりわけ『名づけえぬもの』)においてひとつの頂点に達したと言われる。それらの作品はのちのヌーヴォー・ロマンの先駆けともなり、また『マロウンは死ぬ』における「“私”がさまざまな物語をメモに書き付けていく」という形式は、メタフィクションの大いなる先例の一つとなった。その後の作品、『事の次第』や『伴侶』、『また終わるために』などにおいては、表現する言葉そのものを切り詰めつつ更なる作品の可能性を探求することに努力が費やされた。
アメリカの作家ドン・デリーロは、読み手の世界の見方そのものを変えてしまう力を持ちえた作家として、カフカとベケットの名を挙げている。」
(Wikipedia、https://ja.wikipedia.org/wiki/サミュエル・ベケット)
私は特に彼の作品の「伴侶」に影響を受け、何度も何度も読み返しました。そして書き上げたのが、2001年の散文詩の形式をとった処女作、「記憶の道端」だったのです。この作品には、私が詩を書くことを意識したきっかけとなった、谷川俊太郎先生が、帯文として言葉を添えてくださいました。望外な名誉として受け取っています。
長くなりましたが、これが私の「言葉」への思いです。
次回は、この言葉がその後どのように変化していったかについて、語ってみましょう。
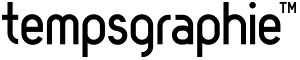

 English
English